2019年12月
※今月のメッセージに代えて、『北海の光275号』に主教告辞が掲載されています。
2019年11月
「このジャガイモ、あんこ入ってる・・」と、妻が言いました。えっ? あんこ? 何のことを言っているのかすぐには分かりませんでした。この「主教室より」で、何度か北海道弁の話を書いたことがありましたが、未だに私の知らない北海道弁がありました。
「ジャガイモのあんこ」というのは、どうも、大きく育ちすぎたジャガイモの真ん中が黒くなっていることを意味するようです。種イモなど特に大きいジャガイモにそうなっていることがあり、こちらの言葉で「あんこが入っている」と言うようです。誰でも、ジャガイモの中が黒くなっていたら、勿論そこは食べられないし、そのまま捨ててしまう人も多いことでしょう。お金を出して買ったのに・・・という思いを持つこともあるでしょう。でもこちらの人は「あっ、あんこ入ってる」と言って、その部分だけを除いて、ほかの黒くなっていないところは大事に料理するのです。その言葉の温かさにしばし感心させられました。
また、「このジャガイモ、中が黒くなっている!」と言うのと、「あっ、あんこ入っている」と言うのでは、そのジャガイモに向き合う私たちの気持ちは明らかに違ってきます。私たち一人ひとりをジャガイモに例えるとしたら、「インカの目覚め」のように、美しい濃い黄色をしていたり、ほくほくとおいしかったり、煮崩れしないしっかりしたメークインだったり、味の良い男爵だったり・・・。そして、そう、中が真っ黒な困ったジャガイモだったり。でも、「わぁ、何だ、このジャガイモは?」とは言わず、「あらあら、あんこが入っていて・・・」と、ていねいにそこを取っておいしく食べてもらえるとなるとどうでしょう。
私自身、きっと、その真っ黒なところをいつも拭い取ってくださるお方がいらして、大事に用いてくださっているのだなぁ・・・と、まな板の上の「あんこの入ったジャガイモ」を眺めました。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年10月
NHKの番組に「ファミリーヒストリー」というのがあります。たまにしか見ないのですが、とても興味深く感じることがあります。本人も知らない家族のルーツを番組が調べて編集し、それを司会者と一緒に本人も見るのですが、想像もしなかった事実があったり、家族の有りがたさに改めて思いを深くしたり、なかなかおもしろいのです。芸術家、俳優、芸能人など、様々な人生を送っている人たちです。普段、ただおもしろおかしく大騒ぎをしているように見える芸能人の背後に、どれほど家族のいろんな人たちが関わり、愛情を注ぎ、大切な時を共有してきたことか。見ているうちに、たいして興味もなかった人の内面的なものに感動を覚えることもあります。両親兄弟、祖父母、曾祖父母・・・脈々とつながる「家族の歴史」というものは知れば知るほど、一人の人間の尊さ、人生の不思議さを実感するものです。
人を知るということ、そこには無限にその人を大切に思う原動力みたいなものが溢れているように思います。ただテレビの画面で見ているだけの人であっても、なんだか調子のいい人だとか、騒がしい人だなどと思っていたことを覆すような、ああこの人にもこんなに豊かな人生があるのだと感動してしまうのです。
私たち自身は自分のファミリーヒストリーをすべて知っているわけではないでしょうけれど、確かにいくつもの人生の上に私たちの人生が営まれていること、そして、誰よりも、私たち自身よりも、ファミリーヒストリーを含めて私たちのすべてを知っていてくださる方が、それぞれの人生を感動をもって見守っていてくださることに改めて思いを馳せるのです。私たちは誰一人として突如作られたわけではなく、たくさんのかけがえのない人の存在と関わりの上に、そして大いなる方のご計画のうちに「究められて」(詩編139:1)いるのです。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年9月
8月の道央分区牧師会で、池田亨司祭による「紙芝居と今井よね」という講話をお聞きしました。1897年、今の三重県津市で生まれた今井よねという女性が、東京の高等師範学校時代に洗礼を受け、卒業後は渡米。神学校で学んで帰国し、伝道のために紙芝居を作ったというお話でした。聖書から「少年ダビデ」、「善きサマリヤ人」、「桑の木のザアカイ」など、またイエス伝シリーズとして、イエスの生涯のいろいろな話の紙芝居を世に出しています。
現代のようにテレビ、パソコン、ビデオ、スマートホンの時代となり、3Dとかヴァーチャル、4Kなどという私のような年代の者には理解しかねる映像・情報が、小さな子どもからおとなにまで氾濫しています。そのような時に、紙芝居の話を聞いて郷愁を覚えました。お年を召した方たち、皆さん、覚えていらっしゃるでしょう。私たちの子ども時代のあの紙芝居のおもしろさと興奮を。木枠の中の絵を必死で覗き込み、話し手の話術に引き込まれた、あの冒険と涙のショー。
教会の日曜学校でも、私たちは紙芝居をしてくれと先生にせがんだものでした。たった12枚の絵から成る聖書の物語やイエス様のご生涯。でも、それは、今思い出してみると、その中に、聖書がきちんと語られ、何が福音のメッセージであるか、子どもたちにでも理解できるように分かり易く描かれていたのです。それらの紙芝居は、今も私の脳裏に鮮明に焼き付いています。
イエス様が人々にされたお話は、たぶん、もともとはとても単純明快であったのではないでしょうか。誰にでも分かる、人々の心を惹きつける、短いお話。それこそが宣教における説教かもしれません。私たち説教者は、ハイテクとスピードの現代にあって、紙芝居の原点に立ち返ってみる必要があるのではないかと改めて思いました。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年8月
晩年、認知症となった父が、母に連れられて病院に行った時の事、お医者さんは父の認知症の進み具合を検査するために、いくつかの質問を父にしました。「今朝は何を召しあがりましたか」。それに対して父は、「ぼくは何でも食べる」と答えたとのこと。「もう少し具体的に」と医師。父は少し機嫌を損ねたように、「だから、ぼくは何でも食べる」と。そこで医師は、「それではこの方はどなたですか」と母を指さして聞きました。父は答えられませんでした。「それではもう一度お尋ねします。この方はどなたですか」。長い沈黙の後、父は、ゆっくり合掌し、おもむろに「祈る人」と答えたそうです。たまたま海外から帰国していて、そこに立ち合った妹からこの話を聞きました。
私の幼少時から、両親が一緒に祈る姿を見てきました。特に、母が忙しかった医師の仕事を引退してからは、いつも朝夕、名古屋では主教邸の礼拝堂で、そして父の退職後は、大阪の小さなアパートの食卓で、朝の祈り、夕の祈りをしていました。私たちが訪ねていった時も、お客さんがいる時も、祈祷書を開き、詩編と聖書を読み、時には母のギターで聖歌をひとつ歌い、代祷表を開いて、世界の教会のため、日本の教会のために祈る二人の姿が必ずそこにありました。
両親が天に召された後、私たちは二人が祈りに使っていた祈祷書と聖書をもらってきて、それを使って同じように、食卓で朝夕の祈りをしています。聖書は、その日の箇所が色鉛筆で示してあり、かなり読み込まれて傷んでいますが、時には、そこに父の書き込みがあるのを見て嬉しくなります。それまでは、それぞれの忙しさにかまけて、二人で一緒に礼拝することは少なかったのですが、今、この時間は、私たち夫婦にとって満たされた恵みの時となっています。
いずれ私が何もわからなくなったときに、妻を見て、祈る人、と言えたらと願いつつ。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年7月
大阪や東京では見られなかったのですが、北海道の新聞には道内の方々の訃報が掲載されます。勿論、道内の逝去者全員ではなく、掲載の了解を得た方だけなのでしょうが、それでも、毎日約百人前後のお名前が載ります。いつもその逝去者欄には、大体目を通すことにしています。教会関係の方でしたら牧師から連絡があるのでわかっているのですが、それでもそこに掲載されているたくさんのお名前を読み、年齢を見ます。
多くの場合、80代、90代、最近は100歳を超える方も多くなりました。数行に書かれている葬儀場と喪主、葬儀委員長の名前。葬儀場が教会になっているのを見ると、「ああ、この方はクリスチャンだったのだ」と何か親近感を覚えます。北海道広しと言えども、一日にこんなにたくさんの方々が人生を終えて逝かれることに、何か感動のようなものも覚えます。
ただ、見ていて、「えっ?・・」と思うこともあります。若い方、子ども。その年齢の若さに、そしてご家族の悲しみを想像して絶句することもあります。親御さんは今、どんな思いで子どもさんを送ろうとしておられるのか。幼い子どもの、若いお母さん、お父さんは・・・。時には、40代、50代の方の喪主がその方のお母さんであったりするとたまらない思いになります。
「死」というものはやはり悲しく、辛い。イエス様が、親しくしておられたベタニアのラザロが亡くなった時に流された涙。おそらく、それはイエス様にとって初めての涙ではなく、幼いころからいろんな人との別れに流してこられた涙であったことでしょう。「死」を「永遠の命」へと根本的に覆す十字架の贖いとご復活は、人間の「死」に対する、主の、はらわたが抉(えぐ)り出されるような憐みの涙から始まったのではないでしょうか。私たちは何よりもまず、「死」が終わりでないことを宣べ伝えたいのです。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年6月
この6月5日は私の執事按手37周年です。ラウンド・カラーを着けた自分の姿を初めて鏡で見た時の何とも複雑な気持ちを覚えています。今日からは聖職者として生きるということに喜びはもちろんありましたが、それ以上に、漠然とした違和感と不安を覚えたのも確かでした。 その年の9月から、大阪教区の教会で牧師補としての働きが始まり、私は執事職の豊かさに目が開かれていきました。最初は、執事はいずれ司祭になるのだから、それまでの準備期間だと心のどこかで思っていたのですが、それはとんでもない間違いでした。三聖職位(執事、司祭、主教)は、その一つひとつが、異なった独立した働きを与えられていて、それらは教会にとって欠くことのできない重要な要素となっています。まさに、教会の歴史の中で、三聖職位があったからこそ、教会は十全な働きができてきたと言えるのだと思います。
執事としての働きはいろいろありますが、聖餐式の中でそれらはよく表されています。執事は、聖餐式で福音書を読みます。会衆が起立する中でキリストの福音を厳かに読んで聞かせます。つまり、人々の中に入って行って福音を伝える先鋒になります。代祷を捧げるのも伝統的には執事です。人々の生活の中にある祈りの課題を自ら調べて、それを教会に伝え、皆で祈るのです。懺悔(ざんげ)を呼びかけるのも、捧げもの(献金)を呼びかけるのも執事です。そして、聖餐拝領では、聖卓を整え、聖杯(チャリス)を捧持します。それは、イエス様のご聖体、即ちイエス様ご自身を、病人やお年寄りなど、教会に来られない信徒にお届けする執事の役目を表しています。最後に、「主とともに行きましょう」と人々を励まして送り出すのも執事です。
今、北海道教区には阿部恵子執事と上平更執事がいます。お二人がこの祝福された執事職を精一杯、大いに楽しむことができるようにと祈っています。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年5月
礼拝に来れる信徒が一人になってしまった稚内聖公会ですが、その巡回ではいつも何か特別な感動とお恵みをいただくような気がします。時には私と妻とそのお一人の信徒だけの礼拝。時には旭川から牧師ご夫妻と信徒数名が来てくださいます。そして、いつもお会いするのはカトリックの「イエスの小さい姉妹の友愛会」のシスターたちでした。礼拝でご一緒出来るときもあり、帰りにお訪ねすることもあり、いつもほんの短いお交わりでしたが私たちにとって大きな励ましと祝福をいただきました。
そのシスターたちがとうとう稚内の地を去ることとなったのです。イエスの小さな姉妹たちの修道院は63年前、当時、共産主義体制下にあるソ連の人々を覚えて祈るために、日本の最北端である稚内に建てられました。小さな民家を借り、一部屋をお御堂(みどう)に、大切な祈りの場として生活の中心に置いておられました。お御堂に座ると、その空間には涙が出そうになるくらい深い祈りが満ちています。シスターそれぞれが、海産物加工場や病院などで働き、時には自分たちで作ったものを売って生活の糧を得ながら、祈りに専念し、地域の人々にも仕えられました。今回稚内を去るにあたり、近所の方々、仕事仲間だった方々を、お一人ずつ食事に招いておられるようです。それは、それぞれにいろいろな事情があり、「その方」だけのために時間を割いておられるのでした。私たち聖公会の者たちも、シスターたちにいつも大事にしていただきました。信徒ではなくても、真摯に向き合い、大切にされた多くの人たち。誰もがシスターたちに心を開き、話を聞いてもらい、祈ってもらいました。「神の国の実現」はこんなところにこそあるような気がします。
今回、稚内から福島に引っ越され、未だ原発に苦しむ方たちに寄り添われます。今後のお働きにも豊かな祝福を祈ります。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年4月
先月、東日本大震災8周年の記念行事に出るために仙台に行った際、市内の北山墓地にあるウォルター・デニング司祭のお墓参りをしました。広い墓地の一角、輪王寺というお寺のそばにキリスト教墓地の区画があり、仙台基督教会墓地もそこにあり、聖公会関係者のお墓もその周りにあります。そこからかなり離れたところに、デニング司祭の墓がポツンと立っています。古さを感じさせる質素な墓石の正面には「英國人傳仁之墓」と刻まれています。墓石の左側面には、横文字で「ウォルター・デニング 1846-1913」、そして彼の出身地が「英国デボン州オッテリー、セントメアリー」と刻まれていますが、どこにも彼が聖公会の司祭であったことは記されていません。聖公会墓地から離れ、外国人墓地の一隅に漢字でこのように刻まれた墓が、北海道に最初に聖公会の福音を伝えた宣教師のものであるということは、よほど注意しないと分からないでしょう。
デニング司祭は1874(明治7)年5月16日、英国聖公会の宣教協会CMSから函館に派遣された最初の宣教師でした。まだ切支丹禁制が解けてすぐの時代、筆舌に尽くし難い多くの困難の中で、宣教師として、めざましい功績をあげた人です。まさに、今の北海道教区の生みの親であり、土台を築いた人でした。
しかし、8年後、デニング司祭は神学上の問題からCMSを解任され、傷心で函館を去り、仙台の旧制第二高等学校(現東北大学)の英語教師になりました。函館を去った後、彼が聖公会の教会に行ったという記録はありません。彼がどのような思いでその後の生涯を仙台で過ごしたのかわかりませんが、彼が北海道の福音宣教に全身全霊を傾けたことは事実です。
デニング司祭の墓前にぬかずき、祈りながら、彼の享年が今の私と同じ67歳であったことに気づきました。嗚呼(ああ)、傳仁(でにんぐ)。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年3月
「あぶなーい! ぶつかるーっ!」 昨年12月の日曜日、新札幌聖ニコラス教会への巡回に行く途中、交差点に停車していた車の中で、私は大声で叫びました。ツルツル路面で、私の車もやっと止まってほっとしてバックミラーを見た瞬間、後ろから大きなワゴン車がかなりのスピードで突っ込んでくるのが見えたのです。ドーンという大きな衝撃音と共に私の車は前に押し出され、前の車に追突。私はハンドルをきつく握り、とっさに身構えたので大丈夫でしたが、助手席の妻は、私の叫び声を聞いても、その瞬間に衝撃があり、軽いむち打ち症になってしまいました。その10秒後くらいに、さらにもう一台の乗用車がやはり止まりきれずに突っ込んできて、もう一度、ドーンと前に押し出され、前の車にも再追突。私の車のトランク部分は大破。パトカーが5台も駆けつけて来て、事故検分が始まりました。4台の車が関係する二重事故でしたので、検分が終わったのは12時近く。幸い私と前の車には過失はまったくありませんでした。聖ニコラス教会には電話で、「み言葉の礼拝」を始めておくようにと指示し、やっとのことで教会にたどり着いて、すぐ洗礼・堅信式と聖餐式の感謝聖別に。説教は私のはずでしたが、着いた時には、牧師補の執事が、きちんとその役を果たしてくださっていました。
昨年11月の教区会で、主教の車を購入するようにというご意見があり、私は、まだまだその必要がないと突っぱねていたのですが、この事故で車は廃車となり、早急に車が必要ということで、常置委員会や財政主事、教区事務所、いろいろな方の手配で、昨年暮れに新しい主教車が入りました。
ガソリンの高騰、長距離の巡回、さらに次の教区主教のことも考え、この車が、主の御用のために大いに役立つことを願っています。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年2月
教区会館の庭も一面真っ白。私が最初に北海道で冬を迎えた二二年前に比べると積雪量はずいぶんと減りました。それでも屋根から落ちる雪も加わって庭は正に小さな雪原です。スズメやシジュウカラなど、この時期は餌がないようで、今金の教会で鳥用にいただいてきた青米などを目当てに、早朝から餌台に近い木の枝にとまって待っています。
そのような庭の、ちょっとした雪原で、時々、あれっ?・・・と思うものを見つけます。足跡です。猫・・、犬・・、もしかしてキツネ・・? 猫の姿も犬の姿も普段はほとんど見ることはありません。でも確かに朝になるとしばしば雪の上に足跡がついているのです。それもその日によって足跡が違います。ペアで歩いた足跡、時には、何か争ったような跡が残っていることもあります。
雪があることで、全く想像もつかなかった事実があったことがわかり、ちょっとびっくり、でもなんとなくわくわくします。大雪になって道路が一人通るのがやっとという獣道になったときは、すれ違う人との一瞬の出会いもあります。お互いに道を譲りあったり、その時に一言声を掛け合ったり。「すみません、ありがとうございます」という一言がどれほどその一日を爽やかにすることか。飛行機の欠航、電車の運休や遅延、高速道路の閉鎖、いろいろ困ることもありますし、何をするにもどこへ行くにも時間がかかり、思い通りにいかないこと、この上なし。それでも、私はこの北海道という美しい雪国が大好きなのです。それはきっと、思い通りにならないこの気候に振り回されながらも、それ故に、黙々と生活を繰り返してこられた人々のおおらかさに魅せられたからではないかと思います。
主教 ナタナエル 植松 誠
2019年1月
新年おめでとうございます。この一年、私たちの前に何が待ち構えているか、期待もあり、また不安もあります。
昨年もいろいろなことがありました。嬉しいこともありましたが、悲しいことも辛いこともたくさんありました。北海道胆振東部地震のような自然災害もありました。「どうして、このような悲しいことが起こるのでしょうか。神様はなぜこのような試練を私に与えるのですか」と私は教会でもよく聞かれます。愛する人の不治の病、身内の突然の死、人からのいわれなき中傷など、そのような理不尽としか思えない状況の中で私たちの信仰はぐらついてしまうのです。信徒からこのように聞かれたとき、ほとんどの場合、私はその方を納得させられる模範解答を持っていません。ただ、私がいつも信じている聖書のみ言葉を開き、それを一緒に読みます。それは旧約聖書のエレミヤ記29章11節にあるこのようなみ言葉です。「わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われる。それは、平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである」。
神様は私たちのために計画をお持ちです。それは今、私たちにわからなくても、納得できなくても、神さまのみ旨の中にあり、希望と平和の将来を約束するものだということ。私たちの目には不幸、災いとしか見えないことに対して、どうして・・・・と解答を詮索することをあえて止めて、神さまの私たちへのご計画の中に、それを委ねていきたいと思うのです。
この年、皆様の上に、神さまの豊かなお導きと祝福がありますように。
主教 ナタナエル 植松 誠

 宣教150年
宣教150年 HOME
HOME 聖公会とは
聖公会とは 教会・施設
教会・施設 今月のメッセージ
今月のメッセージ リンク
リンク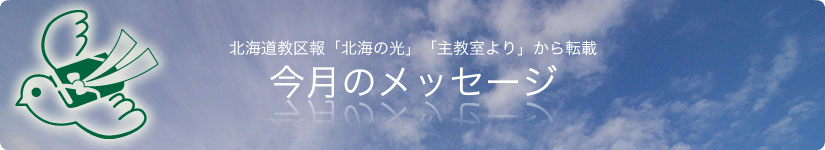
 教役者用
教役者用 会議申請フォーム
会議申請フォーム